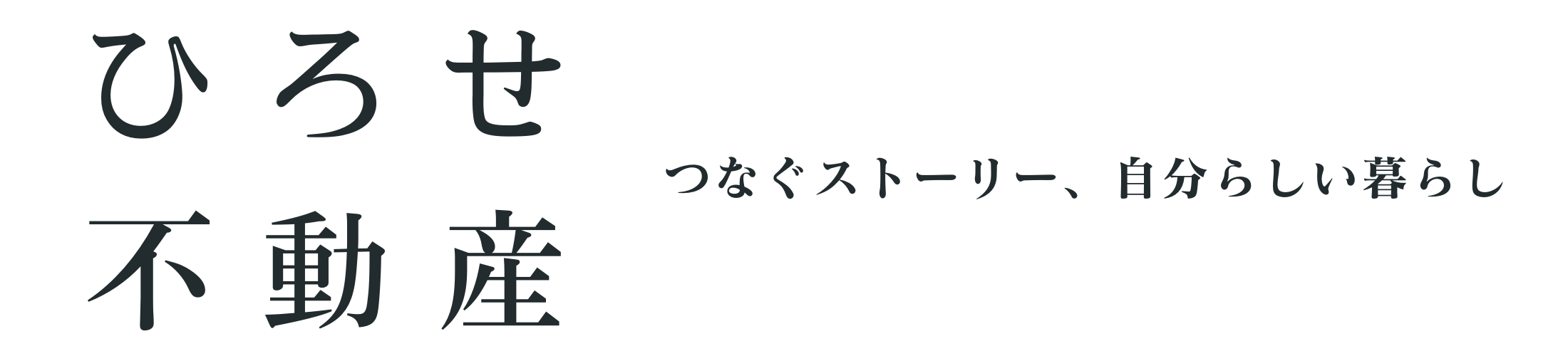1.基本情報
・訪問地: 茂林寺(群馬県館林市)
・訪問時期:2024年5月
2.概要

群馬県館林市の茂林寺は、応永33年(1426年)に大林正通禅師が開山した曹洞宗のお寺です。
寺宝として伝わる分福茶釜は、大林正通に従ってこの地に来た、貉(狸)の化身・守鶴がもたらしたとされる茶釜です。
ここから広く知られる昔話・ぶんぷく茶釜が生まれたと伝えられています。
参道には狸の像が立ち並び、門前町のお土産屋さんにはたぬきの置物やグッズがずらり。
寺の裏手には茂林寺沼が広がり、木道から湿地の自然を観察することができます。
茂林寺の本堂や山門の茅葺き屋根に使われる沼茅(葦)は、この茂林寺沼から採取したものとのこと。
伝説・歴史・自然が三位一体となった地域の象徴として、多くの人に親しまれています。
基本情報
住所:群馬県館林市堀工町1570
アクセス:東武伊勢崎線「茂林寺前駅」から徒歩約7分
拝観時間:展示室は9:00~16:00(火曜・水曜・木曜 定休)
参考:
・茂林寺公式サイト: https://morinji.com/
・里沼「館林の里沼」紹介ページ: https://sato-numa.jp/introduction/01/
3.ひとこと感想

茂林寺前駅を降りると、まずぶんぶく茶釜の狸像がお出迎えしてくれます。
参道には民話を紹介する看板が並び、地域が昔話を大切にしている姿勢が伝わってきました。
門前町は規模こそ小さいものの、昭和の懐かしい雰囲気が残っており、古い町並みが今も生き続けていることに感動しました。
山門や本堂の佇まいからは、時代を超えて受け継がれてきた歴史の重みを感じます。
また、その両方の屋根に使われている茅葺屋根がどことなくぶんぷく茶釜の民話の世界を想像させました。
参道にある狸の像はどれも愛嬌があり、思わず足を止めて眺めてしまいました。
ガラス越しに見ることのできた伝説のぶんぶく茶釜も特別な体験でした。
さらに裏手には茂林寺沼があり、民話のたぬきはここからきたのだろうかと想像が掻き立てられました。
茂林寺界隈は昔話の世界と現実の風景が重なるような場所であり、地域が物語を後世に残そうとする姿勢にも心を打たれました。
古い建物や町並みを訪ね歩く楽しさを改めて感じさせてくれる、貴重な一日となりました。