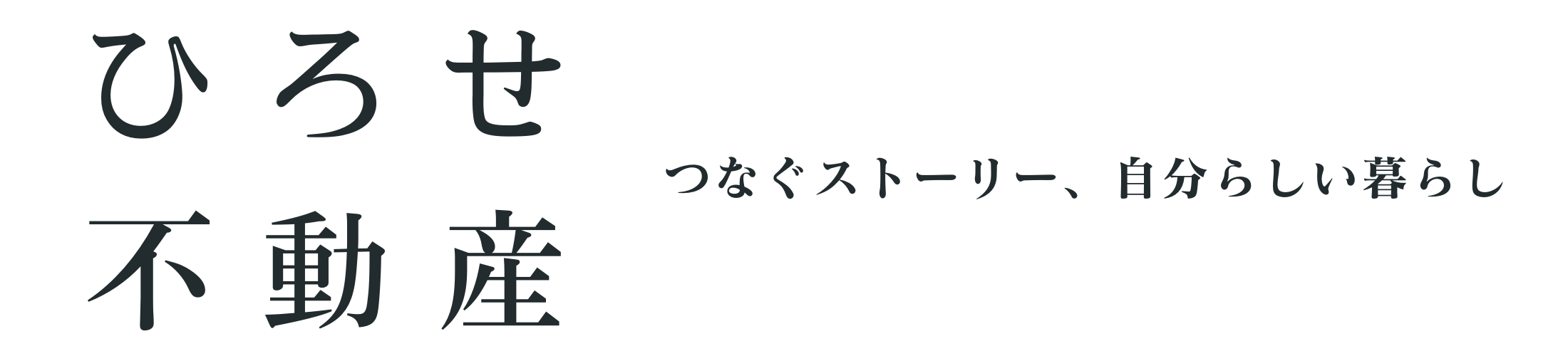先日、所属している不動産業の協会で勉強会があり、参加してきました。
この勉強会は、法律で定められた必須研修(法定研修)とは別に、部会が独自に開催しているものです。
会員同士の交流や知識の向上を目的としていて、まだ実務経験が浅い私にとっては、普段の仕事だけでは得られない学びを広げる大切な機会になっています。
今回は土地家屋調査士さんを講師にお招きし、土地売買の注意点を学びました。
土地家屋調査士さんのお仕事とは
土地家屋調査士さんは、土地や建物に関する調査や測量を行い、その結果を登記簿に反映させる専門家です。
例えば、土地の境界を明確にしたり、建物を新築した際に登記を行ったりと、不動産取引の裏側を支える大切な役割を担っています。
私たち不動産業者も、境界の確認や測量の場面などでお世話になることが多い職種です。
登記にまつわることや現場で起こった事例を具体的にお話しいただき、とても勉強になりました。
公的資料と実際の土地の違い

まず土地調査の第一歩として行うのが、法務局での資料確認です。登記簿や、地図・地図に準ずる図面を調べます。
- 地図は、土地の形や位置、面積が正確に測量されているもの。
- 一方、地図に準ずる図面は、明治時代の地租改正の際に作られた古い図面が多く、あくまでおおまかな位置関係を確認するための資料にすぎません。
現在、全国で地図の整備はおよそ60%まで進んでいるそうですが、残りの40%は今もなお明治時代の図面が使われていると聞いて驚きました。
整備には膨大な労力がかかるため、時間がかかるのも納得です。
また、地籍調査図の整備率を見ても全国平均は52%に対し、宮城県は90%と高水準。
ただし、意外なことに仙台市など都市部は遅れていて、むしろ田舎の方が進んでいるのだそうです。
さらに「縄伸び」と呼ばれる事例もあるとのこと。
これは明治時代、課税を軽くするために土地の面積を小さめに申告した結果、現在の実測と大きな差が出てしまうケースです。
実際に売買の場面で登記簿上の面積と測った面積が違うということが起こり得るわけです。
売買を安心につなぐために
今回学んだことの一部をご紹介しましたが、不動産の売買においては公的な標記と現実が異なることがあるという点が改めて印象に残りました。
土地や建物を次の持ち主へつなぐためには、役所での確認や現地調査、場合によっては関係者への聞き取りまで含めて、丁寧に進める必要があります。
こうした知識をしっかり学び続け、実務に活かしていきたいと感じました。